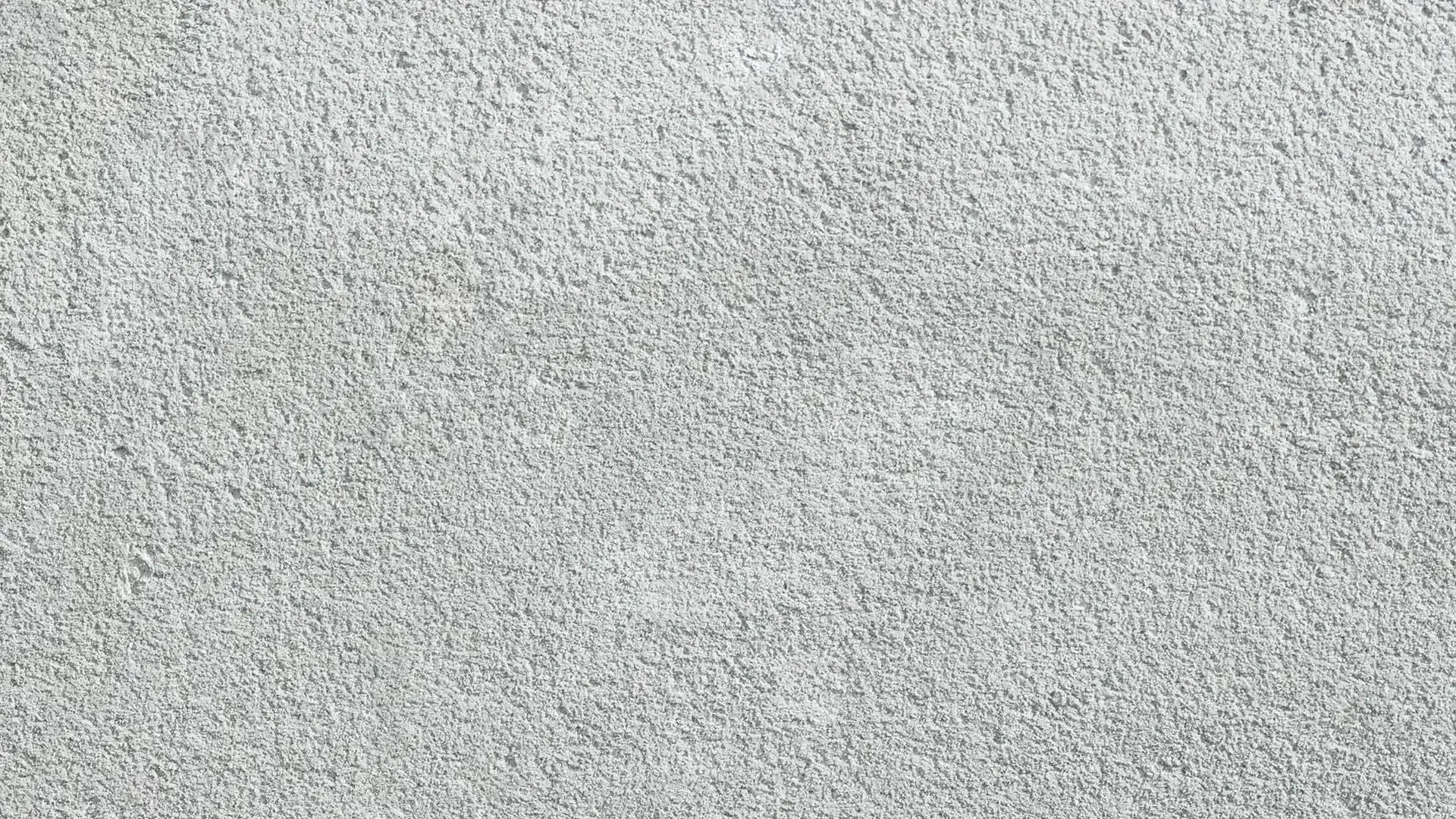皆さんこんにちは。
東京都調布市を中心に、全国各地にて一般左官・特殊左官を軸に建築工事一式を幅広く行っている株式会社ワイズファクトリーです。
「左官職人ってかっこいいな」「手に職をつけてみたいけど、何から始めたらいいんだろう?」そんな風に考えている未経験のあなたに、ぜひ知ってほしい技術があります。それが、左官の基本でありながら、とても奥深い「モルタル仕上げ」です。
今、世の中では機械化が進んでいますが、左官は職人の手でしか生み出せない、温かくて唯一無二の空間を作る仕事。まるでアーティストのように、壁や床に表情を与えることができる、クリエイティブな職種です。モルタル仕上げは、カフェのようなおしゃれな空間から、落ち着いた住宅、さらには大きな公共施設まで、本当に色々な場所で大活躍しています。デザインの可能性は無限大で、あなたのセンスや個性を表現できる場面が多岐にわたります。
「でも、難しそう…」と思うかもしれませんが、モルタル仕上げは左官の技術の中でも基礎の基礎。ここから始めることで、きっと左官の面白さややりがいを実感できます。この技術をしっかり身につけることが、将来プロの左官職人として活躍するための、とても大切な第一歩になるはずです。モルタル仕上げの世界を少し覗いてみませんか?
>左官屋が使う材料はどんなものがある?一例と素材の特徴をご紹介
「左官の仕事、ちょっと気になる…」
私たちは今、新しい仲間を募集しています。
モノづくりが好き、体を動かす仕事がしたい、一生モノのスキルを身につけたい。
きっかけは何でも構いません。
まずは「どんな仕事があるんだろう?」と、求人ページを覗いてみませんか?
▼現在募集中の求人一覧はこちら
左官技術の「核」:モルタル仕上げの基礎知識と主要な材料

参考事例:「東京都 店舗 内装」
左官の世界に飛び込むなら、まず知ってほしいのが「モルタル」という素材です。左官職人にとって、モルタルはまさに「相棒」のような存在。この相棒がどんなものかを知ることは、とても大切です。
モルタルってどんな素材?コンクリートとの違いは?
モルタルは、実はとってもシンプルで、セメントと砂と水を混ぜ合わせて作ります。よく「コンクリートとどう違うの?」と聞かれるのですが、一番の違いは「砂利(じゃり)」が入っているかどうか。コンクリートには砂利が入っていますが、モルタルは砂だけなので、もっとサラサラとした、なめらかな仕上がりになります。このきめ細やかさが、モルタル仕上げならではの美しい表情を生み出す秘訣です。練りたてのモルタルは、まるで粘土のように柔らかくて、コテを使えばどんな形にも自由自在に操れるのが面白いところ。それが時間が経つとカチッと硬くなり、頑丈な壁や床になります。
配合で変わる、モルタルの顔と左官職人の腕
モルタルは、使う場所や求める仕上がりによって、セメントと砂、水の配合を変えることがとても重要になります。例えば、とっても頑丈にしたい場所にはセメントを多めにしたり、ひび割れにくくするために特殊な液剤を混ぜたりすることもあります。こうした配合のバランスを見極めるのが、左官職人の腕の見せ所。天気や気温、湿度によってもモルタルの乾き具合は変わるので、その日の状況に合わせて臨機応変に調整する「勘」と「経験」も大切になってきます。モルタルのことを知れば知るほど、左官の仕事の奥深さが見えてくるはず。この基本中の基本をマスターすることが、プロの左官職人になるための第一歩になるでしょう。
>珪藻土って発がん性があるの?左官のプロが珪藻土について徹底解説
>漆喰って発がん性があるの?左官のプロが漆喰について徹底解説
一言では語れない表情:モルタル仕上げが創り出すデザインの世界
参考事例:「東京都 某店舗 1・2階 内装外装 左官工事」
「モルタル仕上げって、どれも同じような見た目じゃないの?」そんな風に思っている方もいるかもしれませんね。でも実は、モルタル仕上げには驚くほどたくさんの種類があって、職人の腕やセンスひとつで、まったく違う表情を見せてくれるんです。まさに、モルタルはキャンバス、左官職人はアーティスト、と言っても過言ではありません。
仕上げについてもっと知りたい方はこちらをチェック!
>左官の仕上げがしたい方必見!左官仕上げの種類を徹底解説
新しいモルタルの可能性と広がる表現
最近では、ただのモルタルだけでなく、特別な材料を混ぜたり、新しい技術を取り入れたりすることで、さらにデザインの幅が広がっています。例えば、モルタルをまるで彫刻のように造形する「モルタル造形」では、本物そっくりのレンガや木材、石積みの壁を作り出すこともできるんです。また、墨を混ぜて深みのあるグレーにしたり、複数の色を組み合わせてグラデーションにしたりと、「こんなこともできるの?」と驚くような表現が可能になっています。モルタル仕上げは、クールでスタイリッシュな空間から、温かみのあるヴィンテージ風、あるいは和モダンな雰囲気まで、本当に多様なデザインを形にできる、まさに「表情豊かな素材」なんです。
>特殊左官って何?一般左官との違いを徹底解説
>洗い出し仕上げとは?伝統的な左官工法の奥深さと難しさ
未経験からプロの技へ:モルタル仕上げの施工工程と職人の「腕」

モルタル仕上げは、単に材料を塗れば完成というわけではありません。実は、いくつもの大切な工程を経て、ようやくあの美しい壁や床が生まれるのです。そして、その一つひとつの工程に、左官職人の経験と「腕」が光っています。
隠れた準備が重要、下地から仕上げまでの道のり
モルタルを塗る前に、まず大切なのが「下地処理(したじしょり)」です。壁や床の表面をきれいにしたり、プライマーという下塗り剤を塗ってモルタルがしっかり密着するように準備します。この下地が均一でなければ、どんなに素晴らしいモルタルを塗っても、期待通りの仕上がりにはなりません。まさに、料理の下ごしらえと同じくらい重要なのです。
その後に、いよいよモルタルを塗っていくのですが、これがまた奥深いのです。
荒塗り(あらぬり)
最初にごく薄くモルタルを塗り、下地との密着性を高めます。
中塗り(なかぬり)
荒塗りの上に、少し厚めにモルタルを塗って平らな面を作ります。
上塗り(うわぬり)
さらにその上にモルタルを塗り重ね、最終的な厚みを出します。
この工程が、まさに職人の腕の見せ所です。コテや刷毛を使って、前述したような様々な模様やテクスチャーを作り出していきます。モルタルの乾き具合やその日の気温・湿度に合わせて、コテを動かすスピードや力加減を調整する「勘どころ」が求められます。
職人の「感覚」が品質を決める
モルタルは、まるで生き物のように、その日の環境で表情を変えます。だからこそ、職人はモルタルの練り具合(ねりぐあい)を指先の感覚で確かめたり、塗るスピードを調整したりと、常に臨機応変に対応します。乾燥する過程でひび割れが起きやすいというモルタルの特性に対しても、事前に「ワイヤーメッシュ」という網状の材料を埋め込んだり、「伸縮目地(しんしゅくめじ)」という細い溝を入れたりすることで、大きなひび割れを防ぐ工夫がされています。近年では、薄塗りに特化した高耐久性のモルタル材も開発されており、職人たちは常に新しい材料や技術を学び、最高の仕上がりを追求しています。このように、左官職人の仕事は、基本的な工程を覚えるだけでなく、日々の経験と探求心によって、どんどん深まっていく魅力があるのです。
>左官屋さんの仕事とは?詳しい業務内容を解説
>左官はやめとけ?リアルな左官職人の本音を大暴露
モルタル仕上げの真実:メリット・デメリットから見る長期的な魅力と注意点

どんな素晴らしい材料や技術にも、光と影、つまりメリットとデメリットがあるものです。モルタル仕上げも例外ではありません。未経験から左官の道に進むなら、その両面をしっかり理解しておくことが大切です。
知っておきたいモルタルの「光」:デザイン性と機能性
モルタル仕上げの最大の魅力は、なんといってもそのデザイン性の高さです。職人の手仕事によって生まれる、世界に一つだけの表情は、つなぎ目がなくシームレスで、どんな空間にも洗練された雰囲気をプラスしてくれます。クールでモダンな空間はもちろん、温かみのあるヴィンテージ風、和風、洋風、どんなスタイルにも合わせやすい柔軟性があるんです。また、セメントを主成分とするモルタルは耐火性にも優れており、火に強いという機能的なメリットも持ち合わせています。デザインと機能、両方を兼ね備えている点が、モルタルが多くの建築現場で選ばれ続ける理由ですね。
見ておきたいモルタルの「影」:長期的な美しさを保つために
一方で、モルタル仕上げにはいくつか注意しておきたい点もあります。
一つは、乾燥する過程で起こりやすいひび割れです。完全に防ぐことは難しいのですが、前のセクションでご紹介したワイヤーメッシュや伸縮目地などの工夫で、目立つひび割れを抑制することはできます。また、表面に凹凸のあるデザイン(例えば、スタッコ調仕上げのようにザラザラとした質感のもの)は、その特性上、汚れや水アカ、カビ、苔などが付着しやすい傾向があります。これはモルタルだけでなく、似たような質感を持つ他の左官材でも共通のリスクがあります。せっかく綺麗に仕上げても、汚れてしまっては残念ですよね。そのため、屋外で凹凸の大きい仕上げを選ぶ場合は、定期的な清掃やメンテナンスがより重要になります。もし、汚れを極力避けたい、という場合は、室内の壁や床にモルタル仕上げを採用するのも良い選択肢です。最終的な仕上がりが職人の腕に左右される点も、デメリットとして挙げられますが、だからこそ熟練の職人がいる会社で学ぶことが何よりも大切になります。
>姫路城にはなぜ漆喰が使われた?その理由と左官が支える世界遺産の美しさ
>法隆寺は誰が建てたの? 法隆寺と左官の関係や「版築仕上げ」について解説
モルタル仕上げから広がる左官の世界:あなたのキャリアを始めるために
ここまで、モルタル仕上げがどんな素材で、どんな種類があり、どのように作られ、そしてどんな魅力と注意点があるのかを見てきました。モルタル仕上げは、左官職人の技術の基礎でありながら、その応用範囲や表現力は本当に無限大です。単に建材を塗るだけでなく、職人の手によって空間に唯一無二の個性や温かみを吹き込む、そんなクリエイティブな仕事なのです。
左官職人という選択肢:未経験からの挑戦を応援する業界
現代の左官業界は、伝統的な技術を大切にしながらも、新しい素材や施工方法を積極的に取り入れ、常に進化し続けています。そして何より、次世代の職人を育てることに力を入れています。かつては「職人の世界は厳しい」というイメージがあったかもしれませんが、今は未経験からでも安心して飛び込めるよう、丁寧な指導体制や資格取得支援など、サポートが手厚くなっている会社も増えています。
あなたの「やってみたい」が未来を創る
もし、この記事を読んで、「モルタル仕上げって面白い」「左官の仕事、やっぱりやってみたい」と少しでも心が動いたなら、それはあなたの新しいキャリアへの扉が開かれつつあるサインかもしれません。左官職人の仕事は、技術を身につけるほどにできることが増え、自分の手で空間を創り出す大きなやりがいを感じられるはずです。一つ一つの現場で、お客様の理想を形にし、感謝される喜びは何物にも代えがたいものです。
私たちの価値観や、具体的な仕事内容、そして職人育成への取り組みについて、もっと詳しく知りたいと感じた方は、ぜひワイズファクトリーの採用ページもご覧ください。あなたの「やってみたい」という気持ちを、私たちは全力で応援します。
>代表インタビューはこちら!
>従業員インタビューはこちら!
未経験から左官職人になれるワイズファクトリーとは?

株式会社ワイズファクトリーは、全国で一般的な左官から特殊な左官まで幅広く対応し、未経験から多くの左官職人を育てている会社です。現在、左官職人として一緒に働いてくれる仲間を大募集しています。
研修は、一人前の左官職人を育てるために考え抜かれたものであり、技術を磨くために必要不可欠な内容を組み込んでおります。左官の仕事は、日々の努力や探求が欠かせないため、弊社では「躍進し続ける」をテーマに技術を磨き続けております。勤務時間の他に、昼食と午前・午後で計2時間の休憩があり、1日7時間労働です。基本的に土日休みであるのに加え、GWやお盆、年末年始の休みも気兼ねなく取れるので、家族との時間をしっかり確保できます。年3 回の賞与もあり、安心して働ける環境です。経験者の方は給与にしっかり反映しますので、これまでの経験をお伝えください。
左官の仕事に興味がある方・手に職をつけたい方は、ぜひ弊社へお気軽にご連絡ください。左官という伝統技術を継承しながらセンスを磨き、お客様の理想を一緒にかなえていきましょう。